避難
住み慣れた家でも、いざ避難しようとするとあわててしまいがちです。
いざというときあわてないためにも、避難方法を考えておきましょう。
また、各家庭により避難の方法が違ってきますので、それぞれの家庭に応じた独自の避難方法を考えておくことが大切です。
避難の心得10カ条
1 まず、身の安全を図る。
どんなに災害に備えていても、けがをしてしまったら大変です。ふだんから家具類の店頭・移動対策をしっかりと。

2 すばやく火の始末
怖いのは火災などの2次災害。日頃から火の始末の習慣をつける。火元に燃えやすい物は置かない。

3 火が出たらすぐに消火
火災が発生しても天井にまわる前なら消火が可能。火が天井に移ってしまった場合は避難を。1度逃げたら戻らない。

4 戸を開けて出口の確保
特にマンションなどの中高層住宅は、出口の確保を。逃げ場を失ったら避難できなくなる。
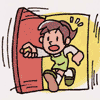
5 あわてて外に逃げ出さない
家の中にいたほうが安全な場合もある。あわてずに状況を見る。外の逃げるときは、瓦やガラスなどの落下物に注意。
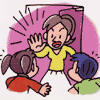
6 狭い路地、ブロック塀に近づかない
落下や倒壊の危険のある場所に近づかない。避難は公園などの広い場所、できるだけ指定の避難場所へ。

7 避難は徒歩で
荷物は多く持たない。車には乗らない。お年寄り、病人を優先に。子どもは手を握って避難する。
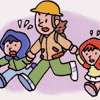
8 山崩れ、がけ崩れに注意
すぐに安全な場所に避難できるよう、ふだんから周辺環境のチェックを。
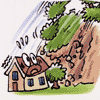
9 応急救護は協力しあって
死傷者が増えると医療機関の対応は限界に。お互いに手を取って応急救護の対応を。

10 正しい情報を得る
デマでパニックにならない。ラジオや市町村、自主防災組織などの正しい情報で的確な行動を取る。
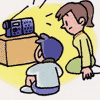
避難のタイミング
- 初期消火ができず、延焼火災の危険があるとき。
- 水害や津波、山崩れ・がけ崩れの危険区域にいるとき。
- 市町村・警察・消防などの非難の勧告又は指示があったとき。
- 自分で身の危険を感じたとき。(自主避難)
※ 自主避難の場合は、避難先を市町村役場や消防機関などに連絡してください。
みんなで支え合いましょう
災害弱者とは
災害弱者とは、災害時に自力避難が困難な人をいい、体力的なおとろえのあるお年寄り、目や耳、身体などの不自由な人、知的障害のある人、外国人やその土地の地理や災害の知識が乏しい旅行者、理解力や判断力をもたない乳幼児などです。災害時には災害弱者を助け、みんなで支え合いましょう。
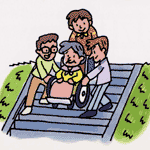
緊急用品チェック
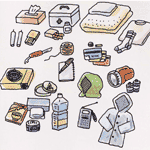
わかっていても、なかなか揃ってないのがこの緊急持ち出しセット。過去の例から、これらがあるとないとでは、災害後の数日間の暮らしに大きな差がでてきます。
※ 水やガスの供給ストップ、食料品や日用品の入手困難といった最悪の事態を考えて、2~3日間しのげるものを備えておきましょう。
※ 背中にすぐ背負えるリュックなどにまとめて入れておきましょう。
※ 非常用持ち出し用の荷物は、1~2個とし、取り出しやすいところに置いておきましょう。
※ 非常用持ち出し品は、ときどき点検したり、期限の過ぎたようなものは取り替えましょう。
